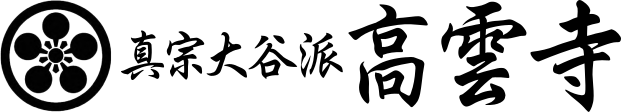寺院沿革


高雲寺の設立(室町時代)
年代は不明であるが(西暦1400年代と推定)足利氏の落人がこの横浜に2~3名留まり、その内の藤本伝喜が向山船場(現在の剱神社北側)に真言宗(弘法大師)の道場を開いたのが高雲寺の始まりとされている。
宗派変更(戦国時代)
文明7年8月(西暦1475年)一向一揆が盛んな戦国時代で、吉崎に居住の蓮如上人は吉崎を離れ、小浜に船で避難の途中嵐に遭い、横浜(資料では杉津)に上陸、当時岡崎の船着き場付近にあった高雲寺に立ち寄り説教を賜って帰依し弟子になる。この時六字名号及び山号『船場山』寺号『高雲寺』が許可され浄土真宗に宗派が変更された。
移設建立(戦国時代~江戸時代)
織田信長が本願寺を滅亡する為全国に戦火が広がり、横浜向山に陣屋が築かれ戦ったが敗戦し、文禄2年(西暦1593年)に道場が消失、浜近くの地に(権左衛門、佐治平、徳兵衛等の所有地)に移設され、その後宝暦11年(西暦1761年)に現在の高雲寺の場所に移設建立された。
山門

寺の山門は廃藩置県のおり、水上嘉兵衛氏が鞠山領主より鞠山城の表門を拝領したもの。丸に剣片喰の酒井家の家紋彫刻版が屋根の左右の切妻破風に付けられている。

天保6年(西暦1836年)に藩主酒井忠毗(ただます)が領内を巡見した際に寄進された船場山の山号額が山門に掲げられている
寺院の様子