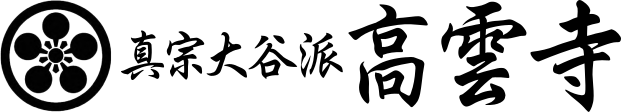Last Samurai とは?
私が住職をさせて頂ける高雲寺では、ジェシーはうちの孫と同じ歳やな、と今まで何回か言われました、、。或いは、うちの息子と同じだね、と。しかし、同世代の子たちは実家を離れて暮らしています、、。
お寺は来てくれないのか、と聞いてみると、いや、お寺には、あまり興味ないみたいな、と少し困った顔で答えがかえってくる。
興味を持ってもらう為に、何ができるのか、これは課題の一つだな、と感じています。
私が息子、或いは、孫と同じ歳なのであれば、私は高雲寺で、いつか、Last Samurai のような存在になるのか、? 最後に残るのは、私一人だけなのか、とその言葉に考えさせられている、、?
過疎化や、門徒さんの高齢化、後継者がいないという問題は、真宗教団が向き合わなければならない重要な事柄である。
長い歴史の寺院であっても、人口減少による過疎化で檀家が減少し、地方では経営危機に直面しているお寺が沢山ある事は想像できる。
お寺の数は多すぎるから、その数が減っていくのは仕方ないのでは、と友達の言葉です。
経済ダーウィニズム(Economic Darwinism)という言葉があるようですが、自然界の自然淘汰(natural selection)と同様、環境の変化に適応できない経済主体は社会から消え、適応可能な主体へと切り替わっていく現象のことをいう。
今の日本が直面している最大の環境変化の一つは、人口減少とそれに伴う地方の過疎化と都市部への集中です。これは檀家によって支えられているお寺の経営を直撃するのは間違いない。
よくあるケースは、進学のために地元を離れた子どもたちが卒業後に戻ってこないというものだ。しかし、それだけでは檀家の寺離れは起きない。実家がまだ残っているからだ。
お寺にとって大事なことは、実家の両親が他界した後、子どもが実家に戻ってくるかどうかでしょう、、。もし、子どもが都市の公営墓地などと契約すれば、実家の墓はほぼ放置された状態になってしまいます。こうした現象こそは檀家数の減少につながる。
上に書いた問題により、門徒軒の少ない、小さなお寺は住職を見つけることもますます難しくなってきたのは現状です。そして、跡継ぎのいないお寺はどうなるのか、?
選択肢は、以下のいずれかでしょう、所属する宗派に跡継ぎを派遣してもらうか、知り合いの住職に代表役員を兼任してもらう。
これらのいずれもできなければ、檀家ゼロ、住職不在、境内荒れ地、建屋ボロボロで、宗教法人格だけ亡霊のように残ることになる、、。
しかし、今まで代々と長年に渡ってお寺を支えて来られた門徒さんは、住職を迎える価値がないのか?
Last Samurai になるとしても、このお寺や門徒さんの為に力になりたい、共に歩ませて頂きたい。
高雲寺の前住職や門徒さん、地域の方々がいかに仏法を大切にして来られたのか、また、真宗教団への厚い思いを持っておられるかがよく感じられます。その厚い思いこそ信心でしょう。
過疎の地域での活動を、これから色々考えていきたい、その気持ちでいっぱいです。聞法会やコンサートがその第一歩となります。
参加してくれる方々とのやり取りを通じて、大谷派僧侶の一人として、皆さんの思いに応えるように頑張っていきます。