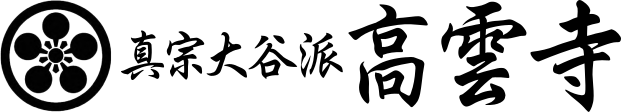積極的に差別をしていなくても、消極的に差別を支えてきた、支えている自分を知る
お説教し始めると、私たちと同じ道を歩んでいる信者であったと認識し、サンガの心が生まれてくる
「自覚無き差別」していませんか?
自分は差別していないと思い込んでいるが、実際には色々と偏見あるのは間違いないです。
大阪難波別院差別事件を学院で学ばさせて頂いたが、その事件があったから、学院に科目としての部落差別があるようになったでしょう、、。しかしそれは歴史的な出来事として語られているところがあり、差別をしている自分が問題にならない。差別は自分自身が問題にならない限り、差別意識も変わらない。
今日は倉吉市人権文化センターにご縁を頂いて、たくさんの方と触れ合いを持たせて頂き、非常に有り難い、貴重な時間を過ごさせて頂きました。部落差別についての学びも深めたと思います。
浄土真宗の世界で、差別までは言わなくても、外国人に対する偏見を感じる事はあります。外国人だから、、仕方ない、ようなニュアンスをですね。浄土真宗の僧籍を持ちながら日本に住んでいる外国人は数少なく、直ぐに比べるがちです。あ、あの人と同じだな!と。しかし、日本人は人によって様々であると同じくて、私たち外国人も、今まで歩んで来られた道も違えば、浄土真宗に出遇ったご縁、または真宗の教えの受け止めも異なります。
日本人と比べて意見や考えをはっきりと述べる人が多いかもしれないけど、これも既に偏見の一つでしょうね。
ですから、一概には言えない、私たち一人一人に出逢って下さい!出逢ってから、判断、評価してください。第三者から聞いた話しではなく、自らの出遇いを通すことです。
スイスは教会離れによって、牧師なりたい人も少なく、インドから牧師を連れてくるのはドイツやスイスの現状です。スイスの田舎は黒人はいまだに指さされる程珍しくて、村の教会の牧師がインド人であるなんて、かなりの壁がある。皆が反対するのも想像できるでしょう。しかしその伝統文化の違う国からきた牧師が聖書を開き、お説教し始めると、私たちと同じ道を歩んでいる信者であったと認識し、サンガの心が生まれてくる。
私自身こそ何回もこの現状を実感させて頂いている。
法話の後抱きしめてくる門徒さん、手を握りたい方、毎回あると言っても良いぐらいです。私の話しは素晴らしかったからではなく、心中不思議なはたらきによって、言葉で表しきれない繋がりが生まれたからです。
最後になりますが、差別は様々な形で現れていると思います。積極的に差別をしていなくても、消極的に差別を支えてきた、支えている自分を知る、これこそがサンガの本当の意味でしょう?
受け取る側に問題があると考え、敏感すぎる、考えすぎ、と簡単に評価してしまう。