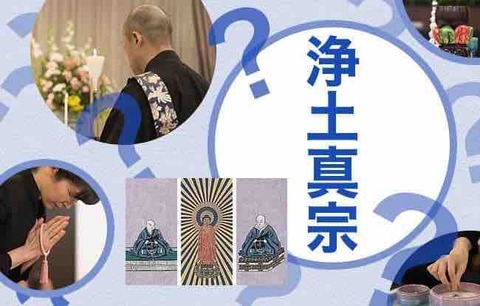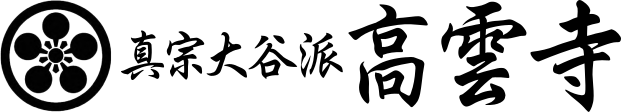浄土真宗の僧侶は禁句にうるさい
浄土真宗の僧侶は禁句にうるさいと、葬儀屋のスタッフに言われて、正直に、ちょっと驚きました。
ご弔電は、その人の選んだ言葉を尊重すべきのではないか、と思います。
世間一般に使われている表現でも、浄土真宗ではその教えから、葬儀や法事などの挨拶で使わない言葉があるようです。 例えば、「冥土に旅立つ」「冥福を祈る」「天に召される」「草葉の陰」などの表現は禁止されていると。また、旅立ち ご冥福、永眠、天国、魂、御霊前は禁句となっていると。
しかし、御弔電まで直されるのは正直あまり理解出来なくて、? これは亡くなられた人に対する気持ちであり、最後に伝えたいメッセージであるから、私たちの個人的な考え、あるいは宗派の決まり事を押し付ける必要がありますでしょうか?
浄土真宗では、亡くなるとすぐに仏になるという考えなので、香典袋の上書きは「御霊前」ではなく「御仏前」とするのがマナーであるのは分かります。しかし、何故、霊にそんなに反応するのでしょう?
また、浄土真宗では、生きているうちに信心を獲得した門徒は、亡くなるとすぐに南無阿弥陀仏によって極楽浄土に導かれ、仏になると考えられているから、葬儀においても他の宗派のように、成仏を祈ったり、死の旅に出るための準備をしたりする儀式は必要ない事ももちろん分かります。
浄土真宗では亡くなるとすぐに浄土に往生することが約束されているので、死出の旅に出る必要もなければ、何度も裁判を受けることもない考えも了解しています。
一般的な風習となっている「清めの塩」、もともとは日本古来の宗教観に由来するものですが、浄土真宗では死をけがれとする考えはないので、必要ない事を説明するのは大切だと思いますが、
御弔電は、その人の選んだ言葉を尊重すべきのではないか、と思います。もう少し広い心が望ましいだな、と私の個人的な考えです。