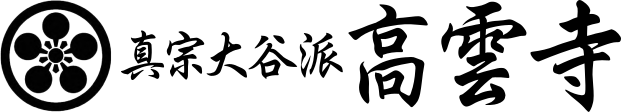法蔵菩薩の物語のなぜ?を考えさせていただくご縁
法蔵菩薩の物語のなぜ?を考えさせていただくご縁、
なぜ?どうして?の疑問を持ち続けることこそ、阿弥陀さまのことを知らせていただくご縁として受け止めたいことです。
西洋人には手を合わせる習慣がないな、と最近気づきました。キリスト教の信者なら、教会では手を合わせるが、信者でない人は教会に入る事もないです。ですから大体の人には馴染みのない事です。
日本で、合掌とは、仏教では仏様への礼儀として合掌する習慣があり、日ごろなじみのあることでいいますと、神社、仏壇やお墓の前で合掌することがあると思います。
しかし必ずしも心が伴っている訳でもないです。
触るとご利益があるとされるものは日本中に色々あり、皆が長い列に並んでいるのを見ると、不思議に感じています。ビリケンさんもその中の一つです。
また、撫牛を撫でて諸病や学問成就が叶うものがあります。
この言い伝えかmythを信じているのか、と友達に聞いてみると、いや、別に信じていないが、まあ、何かいい事あるかも、という気持ちを話してくれました。
私はつい、これ、本当かいな?!という疑問が湧き、信じないものには手を合わせたくない気持ちになります。
法蔵菩薩の物語に関しても、私は同じ観念だな、と気づきました。この物語はあり得ない、どのようにして信じたら良いのかな、と。
キリスト教の場合も物語なのでは、と言われて考えさせられました。確かに、全てが100%正しいとは思わないが、一応キリストという方が実在したのは確かです。歴史的事実は物語より信用性あるかどうか、と問われると、答えに悩みます。
物語をどう受け止めるかでしょう? 物語は何を伝えたいか、でしょうね? 皆さんはどのように受け止めていますか?
安田理深の法蔵菩薩の受け止め方だと少しは頷けます。自分の外にある阿弥陀、英語ではdualistic と言いますが、それを受け止めるのはちょっと苦労しています。
なぜ、法蔵菩薩の物語が語られるのか?なぜ法蔵菩薩を擬人化したのか?それは
『法か真理のはたらきを阿弥陀と名づけて、そのはたらきは私たちのいのちを支えている』
という内容を物語にして擬人化したほうが私たちが『感情移入』しやすいからでしょう。
『法か真理のはたらきを阿弥陀と名づけて、そのはたらきは私たちのいのちを支えている』
という内容を物語にして擬人化したほうが私たちが『感情移入』しやすいからでしょう。
私たちの感情が動くのは、物語です。物語は人の心を動かせます。
なぜ?どうして?の疑問を持ち続けることこそ、阿弥陀さまのことを知らせていただくご縁として受け止めたいことです。