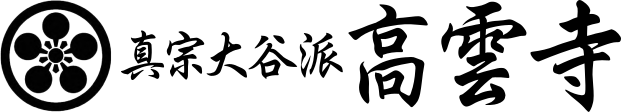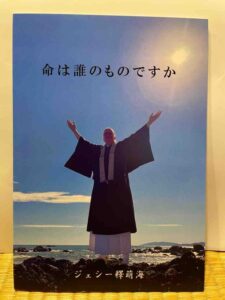生きる意味を分からなくなっている時にこそ
ドイツに起きている深刻な教会離れのイメージです。若い人はもう宗教が必要としないでしょうか?
そう言えば私もスイスで教会に行ったのは、小学校の時だけでした。私こそ宗教を必要としませんでした。
何故仏門に入ったか、何故浄土真宗を選んだのか、とよく聞かれています。親鸞さんに魅力を感じたから、と答えられたら良いのですが、私は浄土真宗を選んでいないのが正直なところです。母の安楽死が縁となり、自らの心に拠り所がないことを傷付かされました。ある日出逢った、「今いのちがあなたを生きている」というテーマが心に響きました。やはり安楽死で積極的に死を早めるのは、命の私有化になると思い知らされました。私にとってその言葉がご縁となったと言っても良いでしょう。ただ、母の自殺幇助があったからこそ、心に響いたと思います。タイミングの問題でもあるでしょう。仏教では縁熟という表現があります。
母の安楽死までは、私も宗教についてあまり深くは考えなかったです。村の98%はキリスト教信者だったが、私は洗練受けていません。学校ではキリスト教と言う科目もあり、皆と一緒に学んでいました。また、親が留守している時、修道院の尼さんに面倒をみて貰い、大人になってからも付き合いありました。
ある日洗練を受けて欲しいと尼さんに言われ、キリスト教の教えについて深く考えるようになったが、教えで納得できないところもあり、そこをクリアできなければ、やはり洗練を受けるべきではないと感じ、受けないことにしました。
人生で何かご縁となる事が無ければ、宗教の世界とはなかなか出逢えないもののではないか、と思います。出逢えないよりも、自ら求めていないですね。
自らで宗教を選ぶ感覚は日本人もあまりないでしょう。教会はこの何年かでスキャンダルが続いて、それが理由の一つとなり、教会離れが起きている今です。
自らある宗教を選ぶのと、その宗教に生きる家庭に生まれるのと、本人の歩みにはどのような影響を与えるのでしょう?
「うちも浄土真宗です」と得度してからよくお話しを聞きました。しかし、その「うちも浄土真宗です」というのは、本人の個人的な選びではなく、家が浄土真宗となってきた流れになっているだけです。家の宗教と言っても良いでしょう。もちろん、それがご縁となり、聞法を続く中、徐々に個人の宗教となっていく事もあります。
スイスではカトリックの洗礼式を生後6ヶ月~8ヶ月ぐらいで受けさせます。
カトリックには「家の宗教」という考え方はありません。信仰はあくまで個人単位のものです。しかしながら幼児洗礼を受けさせるかどうかは基本的には両親の判断です。親はキリスト教の信者であれば、子供に洗礼式を受けさせるのは通常の考えです。
周囲の大人にとっては、「お宮参り」同様、宗教的な意味とは別に、乳児期の節目の通過行事として、終生思い出に残ることでしょう。
カトリックや浄土真宗でも問題は同じですが、「家の宗教だから」の概念から、本人の「信仰」に繋がらない事が多いです。
親が熱心な信者なら、その気持ちが子供に移っていく場合もありますが、やはり、自分の選びではなかった、と違和感のある方が多いです。
信仰は個人と神との関わりであって、先祖や親戚との関わりの中で決めるものではないからです。
洗礼を受けた以上は、信者として登録されますが、心の拠り所としての宗教にはなっていないことから、今教会離れという現象が起きています。
“大切なのは「我-汝」関係“
宗教哲学者ブーバーによれば、世界は人間のとる態度によって〈われ‐なんじ〉〈われ‐それ〉の二つとなる。
スイス人である私なのに、今までブーバーの世界を知ることはありませんでした。日本にきてから初めて知る事ができました。
「In Beziehung sein」das ist für Martin Buber Religion.
Religion bedeutet für ihn, dass Gott in allen Menschen wohne」
神は全ての人の中に住んでいる、
神を一方的に信じるではなく、関係性の中の存在である、これはブーバにとって宗教の意義です。
苦しみは人生の真理が姿を変えたものであり、神があなたと一緒にいるという合図である、と。
というのは、「不安は如来だ」という安田理深の言葉とよく似ています。
「Appearance of the Tathagata within sentient beings」
とも共通しています。
大切なのは「我-汝」関係であり、世界の奥にある精神的存在と交わることだという。そして、精神的存在と交わるためには相手を対象として一方的に捉えるのではなく、相手と自分を関係性として捉えること、
すなわち対話によってその「永遠のいぶき」を感じとることが不可欠だとする。
The relationship is always mutual, not one-sided
神を一方的に信じるではなく、関係性の中の存在である
大垣別院で、私のお話を聞いて下さった方が、質疑の時に、安楽死の問題に関して聖職者はなんと言っているのですか?と質問をしたら、キリスト教の聖職者は、「罪だ」と言っているが、社会がキリスト教が言っていても気にしなくなってしまっている、と聞いてさらにショックを受けた、と。
心の拠り所になっている宗教とはなっていなくて、教会離れの時代となっているのです。自殺は罪とみられますが、その事さえ気にしないのです。
自ら選んでも、そういう家庭に生まれたとしても、宗教は心の拠り所になっていれば、辛く苦しい時に生き甲斐を見出せる力となります。
生きる意味を分からなくなっている時にこそ、教えにたずねていけると思います。