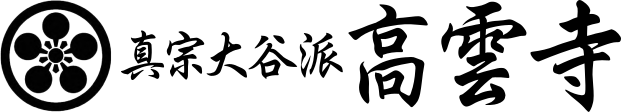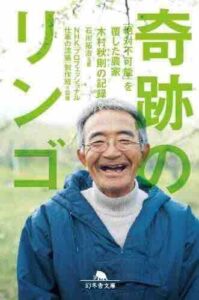いのちの法則
それより前に、いのちって何、何処から現れたのか、と問わなければならないことに気付きました。
何もなかったところに、何処から心臓が現れるのか、未だに不思議です。
そのいのちを生かしてくれている力、その源は何でしょうか、と考えさせられます。
私たちの想いを越えている力の働きです。
雛が孵化するまで17日間掛かりますが、まずは常に37度保つ必要あります。なかなかじっとできない自分の事を考えてみると、17日間ずっと卵温めている鳥の忍耐力に頭が下がります。
しかし、温めるだけで必ず孵化できるとは限らないです。17日間に渡って雛の成長が急に中断されてしまい、中止卵になる事も珍しくないです。
理由が分かりませんが、いのちの成長は何かに中断されます。
このまま続いても、結局生きる生命力がない為、中止卵になるかも知れません。
一番辛く感じるのは、17日間の期間を無事に完了して、孵化の過程自体に失敗するパターンです。
孵化は、小さな生き物にとって大変苦労される仕事であって、結局卵の殻を割って生まれてくる力が足りずに、卵の中死んでしまいます。
ちょっとしたミスでいのちが失われてしまいます。
スイスでは、人と鳥の関係は日本程親密ではありません。鳥に性格あるなんて、想いもしませんでした。
しかし、実際に私達人間とあまり変わらないですね。
好き嫌いが激しくて、妬いてしまったりもします。相手が気に入らなくなってしまう時は殺す事も珍しくないです。
一番懐いていたオスうずらの色は白でしたが、その色は、自分の色と違うとまで認識して、自分と違うものは攻撃されます。人間のスキンカラとよく似ていますね。いわゆる人種差別です。
一緒に生まれ育ったオスの彼女が逃げてしまい、淳君は寂しくなり、夜中まで鳴き始め、困りました。やはり、仲間が必要だと痛感して、うずらは何処で手に入るかを、調べました。
可愛がっていた、寂しくなった淳君の為に、わざわざ名古屋までの旅になりました。オスに追っ掛けられるとメスはストレスになる為、オス一羽に対して、メス3〜4羽が理想だそうです。
人間と同じく、気が合う、合わん問題が出て、一羽のメスとだけ、合わない雰囲気でした。メスは淳君を追っ掛けまわしていました。
まあ、暫くしたら、落ち着くでしょうと、状況を見守っていました。
すると、追っ掛けまわしている事はなくなったが、淳君は明らかに、ちょっと隠れようとしていました。
そこまで切迫詰まっているとは察知できなかったです。
可愛がっていた鳥の苦労を、何故気づいていなかったか、と反省、、。
朝に死んだ事を見つかると、気の合わなかったメスのうずらに対して恨みが湧き上がり、あなたのせいだ!と、泣きながら、そのメスを握り、ケージから庭の方に掘り投げました。
崩れた姿勢で庭に座り、泣いている私が、今やった事は正しくないと分かりながらも、淳君を失った心の傷みが深くて、そうせざるを得ない気持ちでいっぱいでした。
名古屋から買ってきたうずら達は淳君と違い、人間にはあまり慣れていない状態だったから、恐らく一度ケージから出たら、二度と捕まえないでしょう。
しかし、そのメスはずっと鳴きながら私のそばまできたきので、結局手を差し伸べ、簡単に捕まえ、またケージに戻しました。
昼間出かけている間、心が少し落ち着いて、夜に冷静にその子に相手できました。
気が合わなかった事は事実であっても、淳君の死はもちろんそのメスのせいではなかったです。これは私があまりにも辛くて、自分の責任なのに、それをそのメスのせいにしょうとしました。
不思議な力によって生かされている事、いのちの源は、生き物は皆同じくて、この命が終わったら、もとのいのちにかえる、とうずら達に貴重な事を教えて貰いました。
ここまで深くウズラを通していのちの営みを観察することで得られた具体的な体験からの思いを文章に定着させることが大事であると師匠に教えられました。
木村秋則さんもリンゴの木に許しを請うていました。本当に木に向かって声をかけて語りかけたのです。語りかけなかった木は枯れたそうです。