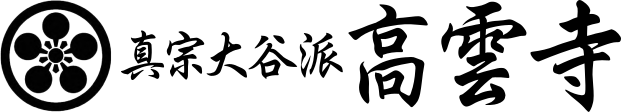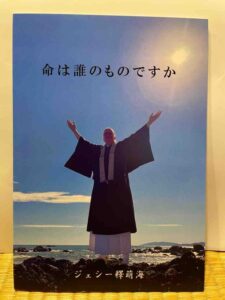父と子の物語を仏教の視点から
キリスト教の父と子の物語を仏教の視点から考えてみました。
ドイツ語では、Der verlorene Sohn
「放蕩息子の帰還」
というタイトルです。
ある人に息子が二人あり、弟が父に財産を分けて欲しいと言う。父が応じると、彼はすぐに遠い国に出かけて、財産を使い果たす。その国に飢饉があり、食べることにも事欠いた。やっとありついた仕事は豚飼いだった。飢えに苦しんだ彼は、父の元に戻り、犯した罪を認め、父の雇い人にしてもらおうとする...
ところが、息子の姿を遠くに認めた父は、駆け寄って放蕩息子を抱きかかえる。下僕に命じて衣服を整えさせ、すぐに肥えた子牛を屠って宴席を設ける。出奔しておきながら、這々の体で帰ってきた弟がちやほやされるのを見た兄は、父に不満を言う。父は兄をたしなめ、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、一緒に祝おうではないかと言った。」
イエスはこのたとえ話により、神の愛の偉大さを教えようとした。話に登場する父は神であり、出奔した放蕩息子は、神から離れた罪深い人を表す。父の下を離れず、勤勉に父に尽くした兄は、ユダヤの支配階級を指すと思われる。彼らは自分の方が正しいのに、罪を犯した民衆が先に救われるのは、道理に合わないと考えた。
キリスト教と仏教は、遠く隔たっている印象を持ちやすい。しかし大乗仏教は、キリスト教の影響で、罪の赦しや浄土という、原始仏教にはなかった概念を取り入れました。
物語について少し考えてみたいですが、
父の前土下座してる次男の姿、
どんな気持ちはそうさせたでしょう?
彼は父に向かって「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。
挫折したからこそ、愚かな自分を父の前に晒し出せました。挫折がなければ、ざんぎの心も起こらなかったでしょう。
長男は真面目に働いてきたのに、
財産を無駄遣いした次男の為にパーティーする、という話しを聞いて
当然、長男がお父さんに不満をいう。
長男の気持ちを、大体の人がよく分かるのではないか、と思います。
面白いのは、キリスト教の信者は、次男を自分のこととして置き換えています、、
神の前立ったら、自分は罪人しかない、いくら良いことしたとしても、
それを認めて、土下座したものは救われる、そう考えています。
私自身は自分を救う道がない、イエスの十字架によって救われると。
キリスト教の信者は、次男を自分のこととして置き換えているが、あえて本当に二男のように人の前土下座できるのか、そこまでざんぎの心が生まれるでしょうか?
仏教では、悪人の救いがテーマになります。
悪人でさえも救われるのだから、善人が救われるのは当然、のは一般的な考えですね。
真宗では、善人でさえも救われるのだから、悪人が救われるのは当然だ、となります。
悪人や善人の違いは何か? 心の持ち方でしょう?
本願他力の趣旨からは外れています。自力で善行に努める人は、阿弥陀の他力にもっぱら頼む心が欠けているため、阿弥陀が助けたいと願った本願の対象とならないのです。
自力の心を捨てて阿弥陀の他力に頼むのならば、まことに極楽に往くことができる。
自力で善行に努める善人ではなく、阿弥陀仏に頼るしかない悪人こそが極楽に往くことができる
長男: おれは一生懸命頑張ってたのに!善人に当たりますね。
次男: は財産を無駄遣いしたから、悪人となります。挫折で無力の自分に出逢ったからこそ、自覚ができたでしょう。
しかし善人にはそのような挫折というか、愚かな自分に目覚める、ご縁となる出来事がなかなかないから、自分こそ善人だ、という考えです。
また、救われている自分に満足してしまえば、そこで立ち止まってしまいます。
阿闍世の救いの物語がらありますが、阿闍世は自分だけの救いで立ち止まらずに、共に救われたい、という願いを起こしました。
キリスト教の物語に出てきた長男は何故お父さんと共に喜べないでしょうか?自分こそは、父の注目、愛、評価を求めているからでしょう。しかし自らの気持ちの自覚がないです。
私たちは次男よりも、長男の立場でしょう。
キリスト教信者は、次男の立場に自分を置き換えていますが、本当に土下座できるでしょうか?
善人は阿弥陀の声に耳が塞いでいます。悪人にはその呼びかけが届いているからこそ、ざんぎの心が生まれるでしょう。
善人は阿弥陀を頼む心がないからこそ阿弥陀の救いの対象になります。
善人にとって何が自らの在り方に目覚めるご縁となってくれるのか、そこが気になります。