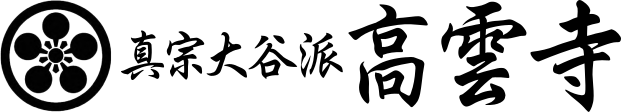人が来る事を待つのではなく、出掛けて行く
人が来る事を待つのではなく、出掛けて行って関わる事も必要!
「この時代に生きる宗教家として」、というテーマで、今日は善念寺で姫路で牧師されている方のお話しを聞かせて頂いた。教会離れ、寺離れ、私たちと同じ課題に直面している事が感じる。
宗教家として問題多きこの時代をいかに歩むかについて考えなければならない。
宗教界にとって大きな影響を与えているこの時代、少子化及び高齢化の時代、、。コロナ禍で人の繋がりが減り、人付き合いは面倒という考えが増えてきた現状、、。
宗教家とは、信仰に生きる存在です。また自らの信仰に命を懸けている者と言える。自らの信仰に固く立って困難な時代をどう乗り越えるかが課題です。
個人的は、お坊さんはもう少し積極的になれた方が良いのでは、と感じている。同朋会や聞法会はよく開催されているが、建物中に行われ、今まで真宗に関わりなかった人には参加しにくいと考えられる。
本来、外の人向けではないからかもしれない。もう既に真宗門徒になっている人を対象にして行われている。しかし、今まで真宗にご縁なかった方々にこそ、来て頂きたい。
イエスが野外で教えを説いているイメージは印象的です。聞法は教会やお寺の中だけでは無く、誰でも参加できる場でもあるのが望ましい。
エホバ証人は何時間も野外の場に立ち、存在感表している。それを加入と考えるかどうかですね?しかし、存在感あるのは確かです。
形は別として、私たち真宗門徒も存在感を表さなければ、門徒数が減る一方のでは、と思っています。
街中でさえ、お坊さんのお参りに行く姿があまり見かけられなくなった。まるで、隠れ念仏かのように、、。玄関で法衣を着て入り、終わった後また着替えて車に、。
以前、東本願寺の門をくくるアメリカ人の親子、、子供が、ママ、この寺はお坊さんいないの?
の問いかけに対して、ママが、いや、昔はいたが、今はもういないよ!と
後ろに立ててその会話を聞いた私は笑わされた、。それぐらい本山でさえお坊さんの存在は薄い事でしょう、。
宗教として持っている信仰を働かせることが求められている。生き生きとして信仰を多くの人に説く必要あります!
宗教家は、時代が変わっても、変わることのない真理を持っているものでしょう。それを語り続ける必要がある。
自らできることにチャレンジすること、生きている人ともっと関わること、
人が来る事を待つのではなく、出掛けて行って関わる事も必要です!