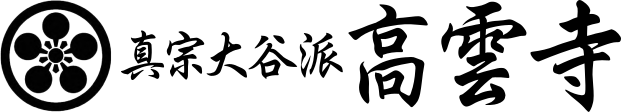如来のはたらきも目に見えないものですが、意識してみれば必ず出遇える
住職のいる寺院だと不思議に、本堂の空気感というか、雰囲気が変わる事が感じられる。もう少し言えば、住職だけではなく、人がお参りしてくれる本堂では生きた教えに出遇える。仏さんの喜びが本堂に漂って本堂は心の落ち着く場となる。
目に見えないものを、どうやって存在している事が分かるのか、どうやって信じられるのか、と問われることがあるが、「愛」の存在を疑う人はいない。身に感じとるものだからこそ。如来のはたらきも目に見えないものですが、意識してみれば必ず出遇える。
The more you get to know him in prayer
The more you accept him in life ,
The more you can see him reflected in the eyes of those around you
尼さんは自身と神の関係性を言葉で表現したのですが、その話しを聞いて、「仏仏相念」という言葉を思い出しました。
「仏仏相念」という言葉は「仏と仏とが相念じる」世界、「あなたのなかにも仏になりたいというこころがある」という本願の心に互いにうなずき、尊敬しあえる世界。
法話のあるべき姿とは、と最近 you tubeでも盛り上がっているが、色々と考えさせられました。意見はさまざまみたいですが、私自身は実際に出遇えたもの、感じたものでないと語れないな、と痛感しています。親鸞さんのお言葉を引用しても、講師自身が頷いているものでないと、おそらく聞いている人にも伝わらないでしょう。
共に考えていく「問いかけ」、課題としての提供、それが大切なのではないでしょうか?答えを出す講師よりも、共に歩んでくださる講師をこそ身近に感じると私は思います。