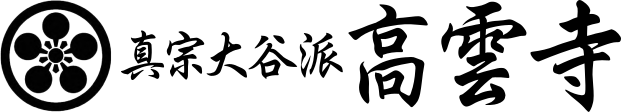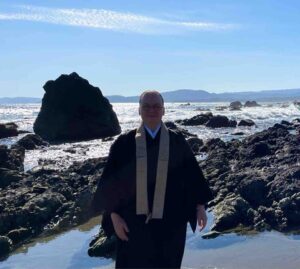我々は、いのちの叫び声を聞いているのか
治る見込みのない難病のなかで、死をのぞみ、それを可能とする医師が薬物を投与し、安楽死を実施します。
肉体的苦痛はコントロールできるようになったにも関わらず、安楽死を申請する人が増える一方です。
「なぜそんなに死にたいか」本当に願っているのは何か、その声に耳を傾けなければいけないと思います。
安楽死を認めることは、死を私物化する、自己の命をコントロールする「死ぬ権利」を認めるということになるでしょう。
しかし、安楽死を認めよという意見が日本国内でも増えています。
母が安楽死を申請しょうと言い出した時、怒りのあまり、彼女が本当に願っているのは何か、と冷静に聞く心の余裕は私になかったです。
真宗の僧侶になり、仏道を歩ませて頂いている今の私は、母の安楽死の希望に対してどう反応するかな、と考えている時あります。
浄土真宗では、無量寿としてのいのちへの目覚めを説いています。私のいのちは私のいのちであるままに私のものという限定を越えた尊厳を持っていることを。
お浄土というのは、生きとし生けるものが光り輝く世界です。現実に生きる私たちは、お互いを光り輝く存在として尊重することが極めて難しい中を生きています。
そのことを自覚しつつ、お浄土という理想を目指して、私にできる勤めを精一杯、この世で果たしていくのみです。
自分がもう役に立たなくなったから死を選びたい、という気持ちになった人を眼の前にした時、自分はどのようなことができるのだろうか。
私たちにはつい何かしてあげようとするが、それも所詮自己満足を満たす為にでしょう。
「not doing but being」your suffering is my suffering 」
何かするのではなく、ただ側にいること、本人が自身の奥底にある声に気付くまで、ただ側にいるだけです。その人の悩みに耳傾けてあげることこそは、「your suffering is my suffering 」が表しています。
安楽死ですが、薬を投与して、命を奪うということは、果たして本当に痛みを和らげることなのでしょうか。
苦しみ悩む人のそばに寄り添って話を聞き、生きていける環境を作り、その人が生を全うできる条件を整えていくことが大切でしょう。
「自らいのちを絶つのが良いとか悪いとか、安楽死の是非が問われているのではない。我々は患者の 本当の願いを聞いているのかが問われている」
人工呼吸器を付けない選択をしていた人が、「悲しむ家族のために死ねない」と思い直したことがある。「これ以上、迷惑をかけたくない」と思う人たちが生きる意味・喜びを見つける、そこにビハーラに取り組む宗教者の使命があると岸上氏。
「我々は、いのちの叫び声を聞いているのか」、その答えを共に仏教に求め続けていきたいです。生きる意味はどのような状態でも必ず存在し、喜びもまた存在します。