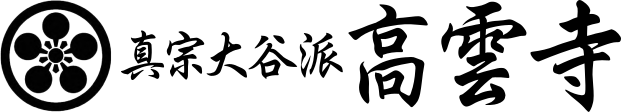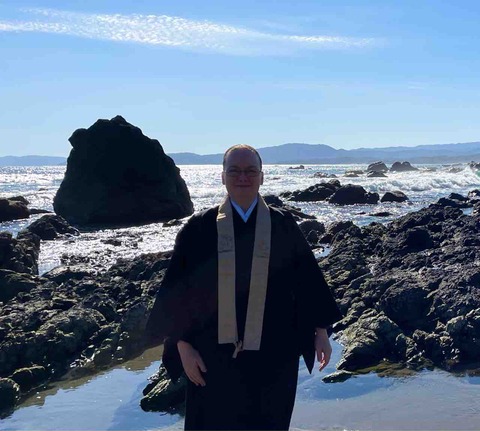苦しみや悲しみを通して、出遇う世界がある
他者の苦しみを自らの苦しみとし、仏さまのお心にかなう生き方
語り合い聞き合う中で自分の思いに気づいていく場、これが何より必要だな、と今日改めて実感しました。
気になるテーマで語り合う中に、日常で気づけない大きな学びと思いを共感できるからです。
今日は、奈良教区仏教婦人会連盟「仏婦・若婦人 研修会」で、「いのちは誰のものか」というテーマでお話しするご縁を頂きました。
何故そんなに死にたいのか、本当に願っているのは何か、その声に気付く為には、一緒に待ってくれる人(善知識)の存在が必要となります。
他者の苦しみを自らの苦しみとし、仏さまのお心にかなう生き方、それを見出していくことです。
一人で気づけないものが沢山あるからこそ、仲間の存在が大事です。
先日安楽死についての番組を見たが、中には、40代で脳梗塞になり、体が不自由になった方がいました。彼の言葉が心に響きました。
“当時に安楽死の制度がなくてよかったわ!きっとあの当時に、僕が選んでしまったでしょう” と。
苦しみや悲しみの真最中だと、周りが見えなくなってしまうのは確かでしょう。だからこそ、苦痛を取り除こうとせずに、大事に味わっていく必要があります。
苦しみや悲しみを通して、出遇う世界があるからこそです。suffering does have value, 無駄ではないです。
安楽死の制度無ければ、うちの母もまだ生きているでしょう。そのレール、死にやすくするレールが用意されている事が危険です。