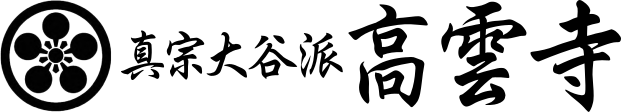Tannisho 第2章は、「Encounter and faith」出遇いがテーマ
Tannisho 第2章は、「Encounter and faith」出遇いがテーマになっていますが、一如にどのようにして出遇えるのかが、今ますます課題になってきました。
「色もなし、形もましまさず。しかれば、心もおよばれず。言葉もたえたり」
その如来の存在を、私たちはどのようにして伝えていけば良いか、ましてや、学問によって分かるものではないです。
ブーバーは宗教との出遇いを、「我と汝」で表現してみました。
われ〜それ Ich-es はErfahrung であり、学問に過ぎません。それに比べて、われ〜なんじ Ich-Du はErleben,または Begegnung 出遇いとなります。出遇いは正に、
「ただ念仏して、阿弥陀に助けられまいらすべし」ということであるから、
自分自身が出遇っていくしかないです。知識は「それ」に過ぎないものであって、「われ〜それ」の経験とは、私が私の思いの中をただ歩き回っているだけである。
「われ〜なんじ」が説いているのは
真実の教えに出遇う世界です。如来の「我〜汝」の呼びかけを南無阿弥陀仏と言う。
ブーバはキリスト教がベースにあるから、私から汝と呼べる、感覚でした。キリスト教徒は自ら「神よ」と人間の方から汝と呼びかけます。
浄土真宗の視点から言えば、分別の身だから、私からは汝とは呼べない。私が如来に願われて、汝と呼ばれ続けていた事に目覚めて、初めて私から汝という言葉が出てくる、と受け取るでしょう。
そこで我は汝であり、汝は我であるという関係性の世界が開かれる。
関係性だから、出遇いが無ければ、関係も成り立たないでしょう。自分の外で求めている限りは、本当の意味で出遇わないのではないか、と思います?
生まれる時に見失った分別を超えた一如の世界に、もう一度出遇うということなんですね。
仏道を歩むのは、エゴを持ちながら、セルフに触れていく、この現実を私たちに教える道である、と表現しても良いでしょうね?
今日は金沢、永光寺にきています。副住職は金沢真宗学院で教えておられる先生でもあり、昨年金沢別院で知り合えました。先生のお寺でお話しするご縁を頂いて、本当に嬉しく思います。
規模の小さな寺院はこれからどのようになっていくのか、色々語り合えました。私たちの世代は様々な面でチャレンジをしていかなければならないのは間違いないでしょう。
しかし、それこそ、「ただ念仏して、阿弥陀に助けられまいらすべし」ですね、、