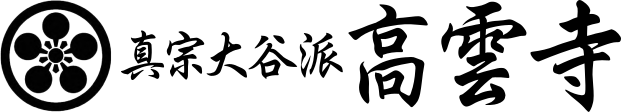何故そんなに死にたいか
安楽死を行う1時間前の母の写真です!老いていきたくない、これからは下り坂しかないから、もういい!とは彼女の最後の言葉でした!
来週の木曜日、10時に死にます!立ち合いますか、と!
今振り返ってみると、彼女のわがままな決断は、私にとって「命は誰のものか?」と貴重な問いに導き、仏道を歩む縁となりました。
2020年7月、京都市内のALS患者の女性に対する嘱託殺人の疑いで、2人の医師が逮捕されました。難病・ALSの進行により運動機能が徐々に衰えてゆく中で、女性は「安楽死を認めて欲しい」と訴えていました。自分の「生」と「死」は自らで選択できるべき、という主張でした。
うちの母も、死ぬ権利ではなく、終末期医療の自己決定権の問題、だとよく言っていました。しかし、it’s my right to die! 、これては本人だけの独断で、決めても良いでしょうか? 「自分が」どうしたいか、だけの問題でしょうか?
しかし、安楽死が合法化されると、さまざまな支援や治療によって生きつづけられる人が、死という取り返しのつかない選択をしてしまうのではないか、さらに「生きたい」と願う人にまで、「なぜ安楽死を選ばないのか」という圧力がかかるのではないか、と懸念されています。
過酷な状況の中で「死」を選びたいと願う人の思いとどう向き合うか、日々の「生」をどう支えていけるのか、そして「安楽死」をどう考えればいいのかなどを、さまざまな視点から伝えるため、皆さんがこの事件からどんなことを感じたのか、声を寄せていただきたいです。
安楽死を自殺と勘違いしないでほしい、と言う声ですが、病気もなかったうちの母の安楽死の独断を、自殺としか言いようがない私です。
この事件で大事なのは、生きる事を選んだ人の死生観を押し付けるのではなく、病気の苦痛に耐えきれず穏やかな死を救いと感じる人が存在するという事を否定せず、その人達の声にこそ耳を傾け真摯に向き合う事だと思います。
・他人の気持ちを完全理解することはできないということ
・難しい問題だと、
死生観を押し付けないでほしい
・当事者の方の痛み・思いは当事者の方にしかわからないのでは